木靴づくりの技術
その他
おおまかな切り出し
 次のオブロングナイフ(Fig9)でブロックを切り出す段階に進む前に、ナイフを研ぎます。
次のオブロングナイフ(Fig9)でブロックを切り出す段階に進む前に、ナイフを研ぎます。
研磨には木製の「砥石」を使います。柳のような固い木でできた長さ60cm・幅7~8cm程度の道具で、両端が細くなっています。
10章の「段階の合間に道具を研磨する」では、職人が日光で焼いた砥石でこの木製の「砥石」を手入れする様子が紹介されています(photo38)。 こうすることで「砥石」の刃に埃のような粒子の小さな粉が残り、ナイフを研いだ時に同時に研磨もされ、非常にシャープな仕上がりになるのです。

ナイフを研いだら切り出しに入ります。 ブロックの一つを作業台の上に置き、片端を腰に当て、反対側のつま先側の端をオブロングナイフが固定されているフックにできる限り近づけます。 このようにすることで、職人がそれほど力を入れなくとも、てこの原理で大きな力が生まれるのです。
この後およそナイフ7振りで、木靴のつま先部分のおおよその形を切り出します。 この作業ではナイフを動かしている方の手だけではなく、ブロックを持っている方の手も適切に動かし、ブロックを移動・回転させながら切っていかなければなりません。 両手を正しく使っている場合は、職人の二本の腕が仕事をしており、体の他の部分は無駄に動かす必要はありません。

次に木靴の「足の甲」部分の形成に入ります。木の加工のしやすさと仕上がりを考慮して、ブロックの幅の広い方の面を使います(photo15)。

かかとの成型が終わったら、オブロングナイフで足を入れるくぼみを(位置と深さに注意しながら)削ります。
足を入れる穴は、深い木靴の場合かかとから全体の長さの2分の1弱くらいの大きさになります。 Fig10を再度ご覧ください。靴底の溝はだいたいつま先から3分の1の位置から3分の2の位置まで、足を入れるくぼみは前から2分の1の位置から始まっています。
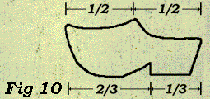
 くぼみが完成したら、オブロングナイフで靴底の溝を仕上げます(photo17のように構えます)。
写真からはうかがえませんが、ここでは木靴を持っている左手の動きが大変重要です。
先述のように最小限の力で必要なカッティングをするためです。
くぼみが完成したら、オブロングナイフで靴底の溝を仕上げます(photo17のように構えます)。
写真からはうかがえませんが、ここでは木靴を持っている左手の動きが大変重要です。
先述のように最小限の力で必要なカッティングをするためです。

Photo18に、木の繊維と垂直に刃が入るナイフの切れ味が垣間見えます。
一つ目の木靴は、いわば「手の感覚で」作ります。
職人はもちろん、長さ・幅・高さなどのサイズを測ることができます(できなければ困ります)が、ここまでの作業では一切測定機器を使っていません。
 Photo19は、幅14cm、高さ10cmの木靴の製作中の様子です。
幅は1~1.5cm縮むことを考慮しなければなりませんが、高さは収縮率が小さく、長さに至ってはほぼ縮みません。
靴底の厚みは、3~4か月の使用に耐えうる程度(2.5CM~3cm)にします。
Photo19は、幅14cm、高さ10cmの木靴の製作中の様子です。
幅は1~1.5cm縮むことを考慮しなければなりませんが、高さは収縮率が小さく、長さに至ってはほぼ縮みません。
靴底の厚みは、3~4か月の使用に耐えうる程度(2.5CM~3cm)にします。

ペアのうち2つ目の木靴を成型しつつ、足を入れるくぼみを比較します。 両方のくぼみが均等で、後に足を入れる穴を掘れるよう十分大きくくぼんでいる必要があります。

靴底を比較する際に重要なポイントは、両方の木靴の靴底同士を合わせた後 (photo22参照)かかと同士を離し、徐々につま先同士が触れるように扇形に開いていった場合、一番最後につま先のポイント同士がぴったり合うということです。



